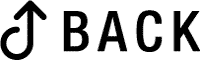堀内からのメッセージ3月31日から4月12日まで多摩美術大学八王子校舎アートテークにて「堀内正弘 退職展」を開催します。直前のご案内となり申し訳ありません。開催場所が遠いので恐縮ですが、もしご機会があればお立ち寄りください。展覧会の内容は、ホームページで順次公開していく予定ですのでどうかしばらくお待ちください。この展覧会のために、私の卒業制作から最近の活動まで見渡した印象は、自分のやりたいことばかり熱中していたということです。反省点も多くありますが、仕事には手を抜かなかったと思います。さて、ご報告になりますが、昨年11月、淡路島で作業中に脚立から落ち、首の骨が折れ、4肢不随の身となり、両手が使えなくなってしまいました。まさに九死に一生を得ましたので、人生の再出発ということで、これからの人生を明るく前向きに歩んで行きたいと思います。幸い、頭脳・目・耳等には全く影響が出ていないのですが、1番好…